墓石の耐久性は非常に高いものが多いのですが、地震大国である日本だと地震対策も考えないといけません。耐用年数と基礎工事の関係性から、耐震設備の施工の具体例を紹介していきます。

暮石は硬くて丈夫な石材でできており永久的にもつものだと思われている方も多いかもしれませんが、どの暮石にも必ず耐用年数はあります。一般的に暮石の耐用年数は国産石を使用した暮石の場合で150年〜200年ほどになっています。
また、暮石に用いられる石材の質によっても耐用年数は大きく変わってきます。暮石は屋外に建てられることが多く、毎日強い日差しにさらされるうえ雨や風も凌ぐことはできません。そのため、自然の力に耐えられる「硬度」や雨の影響を受けにくい「吸水率の低さ」を持ち合わせている石材であるほど、耐用年数は高まります。

「石材の質」が耐久性に大きく関わることを紹介しましたが、実は「石材の質」以上に耐久性に大きな影響を与えるのが「基礎工事」です。基礎工事とは暮石を支える土台を作るために行われる工事のことです。
基礎工事の出来が悪く土台がしっかりとしていない状態では、暮石の重みを支えきれず傾きが生じたりヒビ割れが生じることもあります。また、屋外に建てられている暮石は雨や地震、台風などの影響を直に受けてしまうため、基礎工事の段階で自然の力に耐えれるようにしっかりと設計しておかなければいけません。
暮石の土台はコンクリートで作られています。コンクリートは吸水率が比較的高い素材であり、耐水加工が不十分な状態では雨水が浸透しやすく腐食や劣化を招きやすくなってしまいます。基礎工事が不十分な状態では、長い耐用年数は期待できません。反対に基礎工事がしっかりと行われており強度な土台が築けていれば、暮石の耐用年数を高めることができます。
「基礎工事」はお墓を作るうえで非常に重要ですが、工事方法や使用される資材に統一されたルールがあるわけではありません。そのため、地域によって工事の進め方が異なることも珍しくはありません。一般的にはどのような流れで「基礎工事」が行われるのか、流れをまとめたので、詳しく見ていきましょう。
まずはじめに暮石の建立地を整えるために、雑草等の不要物を全て取り除きます。不要物がなくなったら、土台を地中に埋めるために地面を掘っていきます。掘る深さに関しては周囲のお墓の高さとの兼ね合いや地盤の状態を考慮して30cm〜50cmほどの深さにするのが一般的となっています。
地面を掘る深さは非常に重要で、地盤がお墓の重さに耐えられる深さに留めなければいけません。地面の深さが深くなれば深くなるほど、後で流し入れるコンクリートの量が増え地盤にかかる重量も増えることになります。
地盤が重量に耐えられなくなってしまうと暮石に傾きが生じることもあるので、重量とのバランスを十分に考慮して地面を掘り進めていく必要があります。また、必要に応じて地盤の強度を高めるために、地盤改良が行われることもあります。
土台の下準備ができたら、次は土台の基礎を固める作業に入ります。地盤を強度で安定したものにするために砕石を全面的に敷き詰め、転圧機を用いて固めていきます。
地盤が整えば、続いて納骨室の設置を行います。納骨室を設置の際には同時に排水穴の設置も行います。地下に納骨室がある場合、湿気がたまりやすく結露が生じるケースが多くなっています。また、施工方法や設置場所によっては、地上からの雨水が浸透したり地中から湧いた水の影響を受けるケースもあります。
納骨室が水浸しになってしまうと、遺骨が損傷してしまったりカビが生えてきてしまうケースも珍しくはありません。大切な遺骨を守るために、排水穴を設置し納骨室に水がたまらない状態を作ることが重要となります
納骨室の設置が終わったら、強度を高めるために鉄筋を配置していきます。最後にコンクリートを流し込み、平らにならすと同時に不純物も取り除いていきます。コンクリートが固まれば基礎工事は完了となります。

「基礎工事」の出来で暮石の劣化スピードは大きく変わります。適正な基礎工事が行われていなければ、数年程度でほころびが露わとなり暮石に損壊が生じることもあります。ですから、お墓の土台を作る「基礎工事」は非常に重要なのです。
また、暮石の基礎を作るうえで「基礎工事」同様に重要となるのが「耐震対策」です。特に日本は地震大国とも称されるほど地震の発生率が高い国となっています。近年でも阪神大震災や東日本大震災、熊本地震など地域を問わず全国で大型の地震が多発しています。
今後、南海トラフ地震と呼ばれる非常に大型の地震が発生する恐れがあるという予測もされており、地震対策は十分に行っておかなければいけません。
墓石は一般的にセメントで接着されて組み立てられていますが、セメントの効力は月日と共に劣化してしまいます。劣化し接着が不十分な状態で地震による大きな振動を受けてしまうと、当然墓石は揺れに耐えることができず傾いてしまい最悪の場合倒壊に至ることもあります。
防ぎようのない自然災害により、大切なお墓が壊されてしまうことは非常に悲しいことです。また、地震による暮石の損壊にはさまざまなリスクが潜んでいます。どのようなリスクがあるのか、しっかりと確認しておきましょう。
耐震加工を施していない墓石は地震の影響を直に受けてしまうため、損壊や倒壊につながりやすくなってしまいます。損壊の程度によっては修復が可能なこともありますが、修復費用は被害の程度によって金額が異なり数千円程度で済むこともあれば数十万円と高額な費用が必要となることもあります。
コーキング剤などを用いて自分で修復が可能な場合もありますが、知識のない素人が行うと修復が不完全に終わり結果的に劣化を促進してしまうこともあるので注意が必要です。
また、損壊が大きく修復できない状態になってしまった場合は、新しくお墓を立て替えなければいけません。そのため、修復以上に高額な費用が必要となります。また、崩壊したお墓を廃棄する費用も必要となるので、二重に費用がかかるという点はしっかり頭に入れておきましょう。
地震の影響で所有しているお墓が倒壊し周囲のお墓にも危害を加えてしまった場合は、損害賠償請求をされる可能性があります。損害賠償請求の可否は震度の大きさや立地、管理体制など諸条件を総合的にみて判断されることになります。しかし、震度4〜5未満で耐震加工を施していない場合は、損害賠償請求が認められるケースが多くなっています。
耐震加工を怠たり暮石が倒壊した際は、所有している暮石の修復費用だけでなく他人の暮石の修復費用も必要になる可能性があるので注意が必要です。
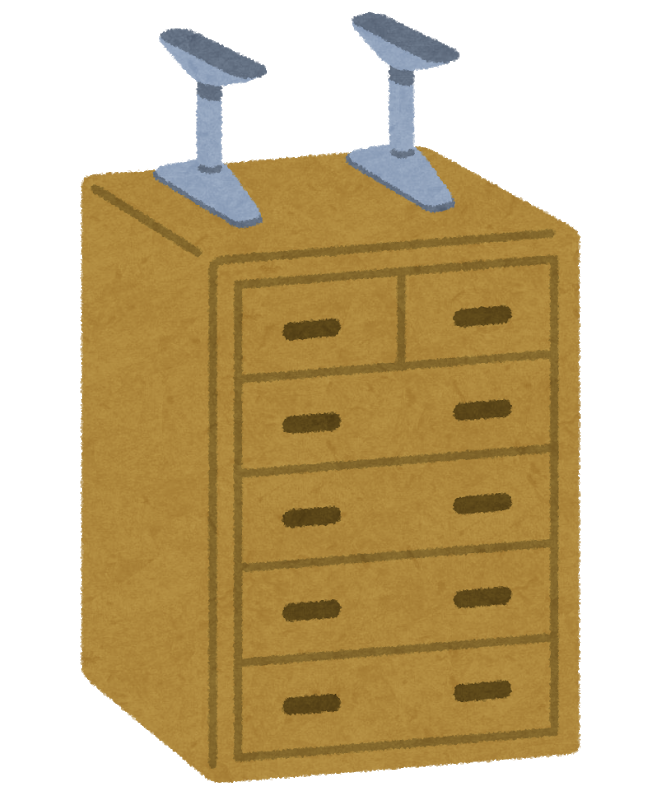
地震から大切なお墓を守るためにはどのような施工を行えば良いのか、具体的な耐震加工をご紹介します。新たにお墓を建てる際に活用できるものだけでなく、既存のお墓に使える耐震加工もあります。既にお墓を建ててしまい耐震加工を施していないという方でも、今から地震対策を行うことは十分に可能です。
「耐震一体墓工法」は竿石/中台/下台を一体化させてお墓を作る方法です。お墓を作る際は分離された竿石/中台/下台を組み合わせるのが一般的となっています。しかし、従来のように一つ一つの台を積み上げる方法では重心が不安定になってしまいます。そのため、揺れが発生した際に暮石が振動をうまく受け止めきれず、積み木倒しのようにして倒壊が起きやすくなってしまうのです。
「耐震一体墓工法」では一つの石材から竿石/中台/下台を一体にしてくり抜き暮石を作ります。一つ一つの台を積み上げる必要がなく、元々一体となっているので地震によって分離する恐れはありません。また、一体とすることで重心が一番下にくるため、地震の振動をしっかりと受け止めることができ倒壊を防ぎやすくなっています。
「耐震ピン工法」は一昔前によく用いられていた工法で、既存のお墓にも活用が可能です。金属のピンを用いて暮石を連結させることで、地震の揺れによる暮石のズレを防ぎます。
ただし、「耐震ピン工法」は横揺れに強い反面、縦揺れには弱いという面もあります。縦揺れが起こった際には暮石が飛び上がってしまうこともあり、衝撃で暮石に損壊が生じてしまうケースもあります。
耐震ピン工法の縦揺れの弱さが懸念され注目を浴び始めたのが「接着剤工法」です。耐震ピン工法では金属のピンで暮石の接着が行われていますが、「接着剤工法」では接着剤を用いて暮石の接着が行われます。
接着剤を使用し暮石同士をしっかりとくっつけることにより、暮石が飛び上がる現象を防ぐことができます。さらに、横揺れだけでなく縦揺れにも強いので、暮石の損壊や倒壊が起こりにくくなっています。
ただし、石材用の接着剤にはさまざまな種類があり、適材なものを使用しなければ資材や紫外線などの影響で効力が十分に発揮されない場合もあります。「接着剤工法」を用いる時は効力をしっかりと出すために、「接着剤工法」の施工実績が豊富な石材店に相談するのが良いでしょう。また、「接着剤工法」も既存のお墓にも適用が可能となっています。
「ゲル」は振動を吸収する効果があり、地震対策に非常に有効的です。震度7の耐震実験をクリアしたものもあり、最大クラスの地震にも対応が可能です。一般的に暮石は竿石や中台、下台などが積み木のように積み上げられて一つのお墓ができています。しかし、各台が分離されていることによりそれぞれの台は限られた設置面でしか重心を保つことができず非常に不安定な状態となり、地震の揺れをうまく受け止められなくなってしまいます。
「ゲル」を各台の四隅に貼り付けることにより「ゲル」が振動をしっかりと吸収してくれるので、地震が発生しても衝撃が伝わりにくくなり倒壊を防ぐことが可能となります。また、暮石の重みに耐えられるよう、耐震用の「ゲル」には耐荷重リングと金属球が埋め込まれています。そのため、暮石の重みで「ゲル」が潰されてしまう心配はなく、しっかりと地震から暮石を守ってくれます。
地震対策として用いられる「ゲル」はシリコン素材のものが多くなっていますが、シリコンは非常に耐久性が高い素材となっています。−60℃〜150℃と非常に幅広い温度に適応可能で耐熱性にも耐寒性にも優れているため、季節を問わずに効果を発揮してくれます。
既存のお墓にも用いることができますし、耐震加工といっても「ゲル」を暮石の四隅に貼り付けるだけの簡単な施工のため多くの時間を要すことはありません。

基本的に墓石は耐用年数が高まるように工夫して作られています。一般的に暮石に用いられることが多い「御影石」は100年前後の耐用年数があるとも言われており、非常に長持ちする石材となっています。
ただし、どれだけ良質な石材を使っていても、暮石の土台が悪ければ長い耐用年数を維持することはできません。基礎工事の出来次第では墓石を立ててから数年程度で、ヒビが入ったり接着が取れ剥離してしまうケースもあります。墓石は屋外に建てられることが多く台風など自然災害の影響を直に受けます。わずかなほころびができてしまうと、隙間から雨水などが暮石の内部に浸透してしまいさらなる劣化を招いてしまう恐れもあります。
また、地震の影響も考慮して耐震加工も十分に行わなければいけません。耐震加工を施していないと、地震が発生した際に墓石が傷つくだけでなく最悪の場合は倒壊し廃棄処分となることもあります。
暮石の耐用年数を決めるのは「基礎の出来」です。ですから、暮石の基礎を築く「基礎工事」や「耐震加工」を任せる石材店は慎重に選びましょう。信頼できる石材店を見つけ、納得のいく形でお墓を建てましょう。
